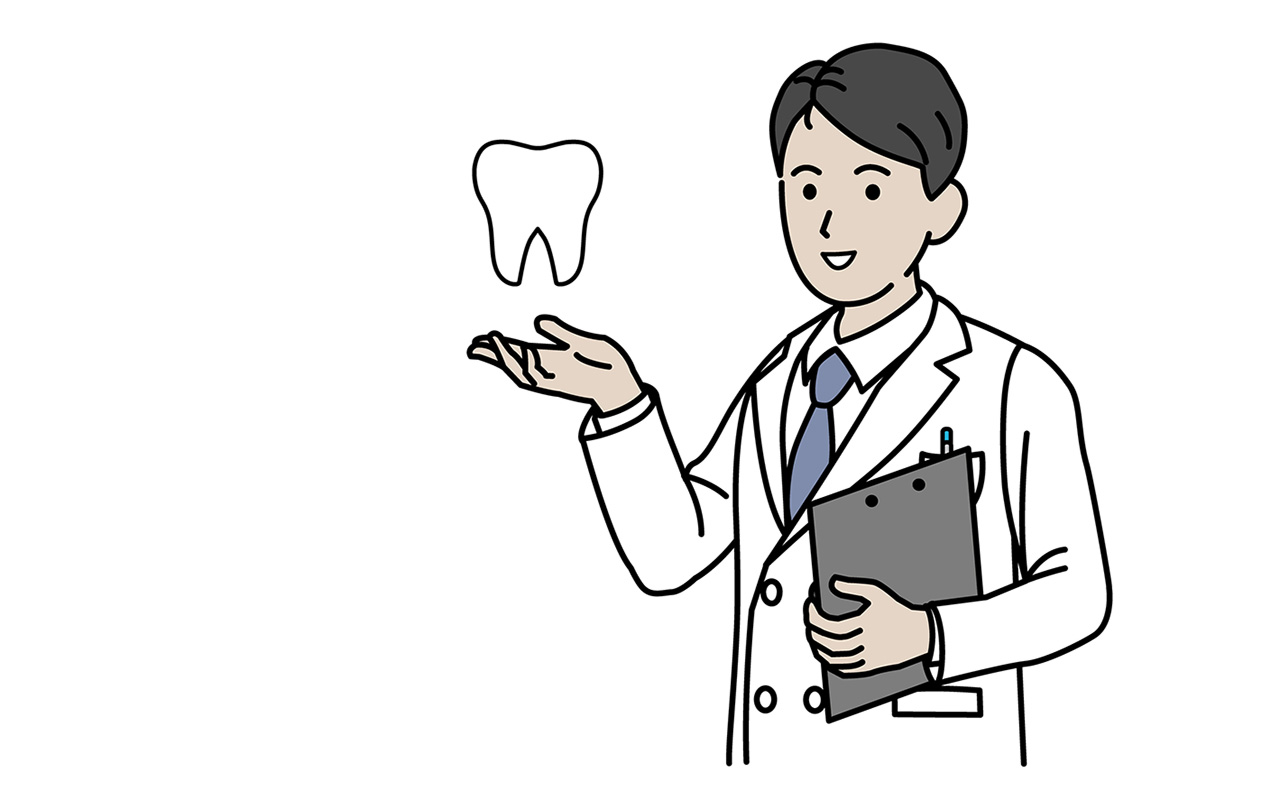
誰しも一度は経験したことがある“歯の痛み”
その背後には、さまざまな原因が潜んでいます。今回はその一部をご紹介します。
-
虫歯(う蝕)
最もよく知られている原因です。歯の表面にできた小さな穴(初期の虫歯)から、だんだんと内部の象牙質、さらに神経(歯髄)にまで進行すると、強い痛みが出ます。冷たいものや甘いものがしみたり、何もしていなくてもズキズキとした痛みが続くことがあります。
-
歯の神経の炎症(歯髄炎)
虫歯が進行して歯の神経にまで達した場合や、強い衝撃を受けた場合などに起こります。ズキズキ、ドクンドクンと脈打つような痛みが特徴で、夜中に痛くて眠れないこともあります。
-
歯周病(歯槽膿漏)
歯ぐきや歯を支える骨が炎症を起こす病気です。進行すると歯ぐきが腫れたり、歯がグラグラしたり、膿が出たりします。歯ぐきの奥がジーンと痛むこともあり、歯の痛みと感じられることがあります。
-
知覚過敏
歯の表面のエナメル質がすり減ったり、歯ぐきが下がって歯の根元が露出すると、冷たいものや熱いものがしみるようになります。一時的な痛みで、虫歯とは違ってすぐにおさまるのが特徴です。
-
親知らずの炎症(智歯周囲炎)
親知らずが正しく生えてこないと、歯ぐきとの間に食べかすや菌がたまり、炎症を起こすことがあります。奥歯の周りが痛くなり、口が開きにくくなったり、顔の一部が腫れたりすることも。
-
歯のひび割れ(クラックトゥース)
硬いものを噛んだときや歯ぎしりの習慣によって、歯に小さなヒビが入ることがあります。このヒビから神経に刺激が伝わると、痛みが出ることがあります。診断が難しく、発見されにくい原因のひとつです。
-
噛み合わせや歯ぎしり
無意識のうちに歯ぎしりやくいしばりをしていると、歯に過剰な力がかかり、痛みを感じることがあります。とくに朝起きたときに痛みが強くなる場合は要注意です。
口の中以外の原因
筋肉や神経、ストレスなどが原因で歯やその周囲に痛みを感じることがあります。これを「非歯原性疼痛」といいます。この場合、歯の治療をしても痛みがなくならないことがほとんどです。非歯原性疼痛は診断が難しいため、早めの受診が大切になってきます。

痛みの種類やタイミングで原因の見当をつけることもできますが、自己判断は危険です。
少しでも異常を感じたら、早めに歯科医院を受診するのが一番です。








